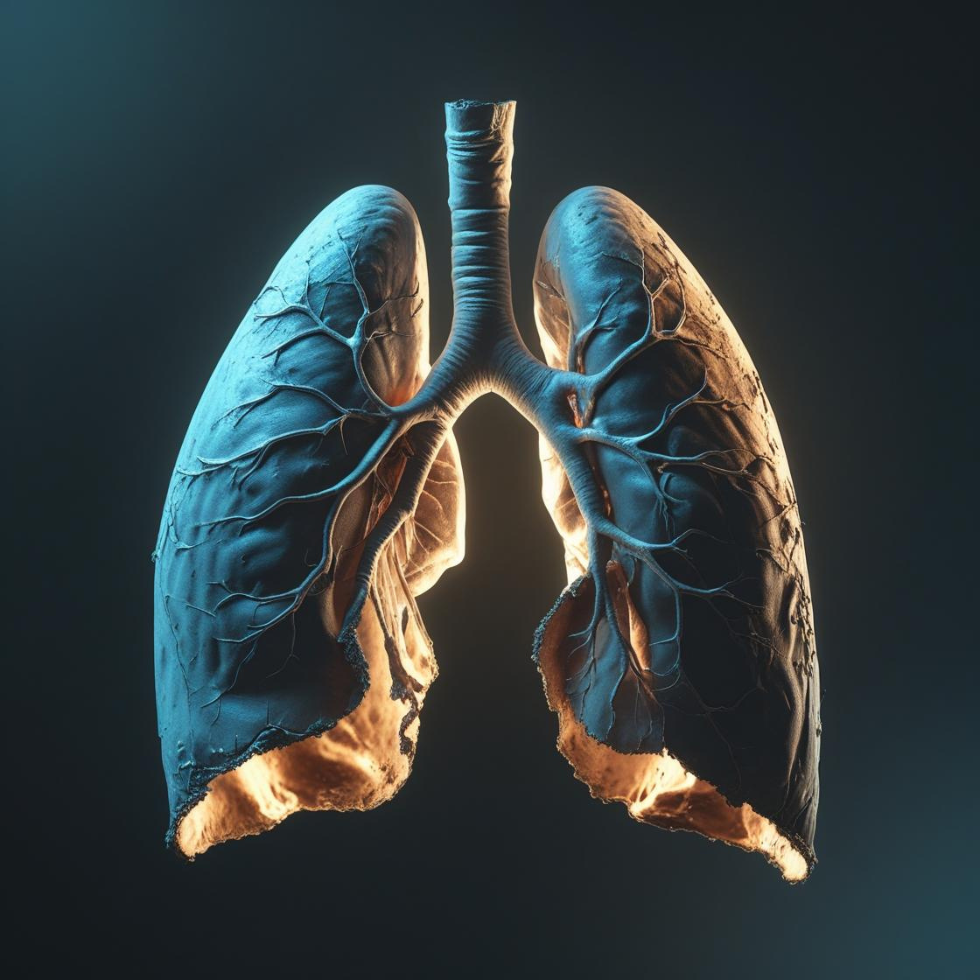さて、前回コラムの最後に高血圧の診断基準は「140/90mmHg」とお話しました。
しかし、じゃあ140mmHg以下なら全く大丈夫なんで、どうでもいいですよ~!
…というわけではなく、実は120mmHg以下は「正常」、120~130mmHgは「正常高値」、130~139mmHgは「高値」と、140mmHg以下でもわざわざ3つに分類されています。(1)
実はこれ、2019年に改定された高血圧ガイドライン でこのように変更されたのですが、それまではそれぞれ「至適血圧」、「正常血圧」、「正常高値」と呼ばれていました。見比べるとわかるのですが、特に血圧130~139mmHgの分類名が「正常高値」→「高値」というように、「正常」の2文字が削除されたんですね。
つまり、「高血圧の診断基準は140mmHg以上だけど、130~139mmHgの血圧はもはや正常ではありません!」ということが明確に発信されたわけです。
これ、なんでこのような変更があったかというと、いろんな疫学研究により、血圧120mmHg以上では血管の病気(前回のコラムでお話した脳心血管病のことです)の発症やそれによる死亡リスクが直線的に上昇していること、そして130~139mmHgの分類に属する人たちも多数含まれていたことからこのように変更されたんですね。(2)
そして一方140mmHg以上の高血圧も、140~159mmHgの「Ⅰ度高血圧」、160~179mmHgの「Ⅱ度高血圧」、180mmHg以上の「Ⅲ度高血圧」に分類されています。こちらはまぁ説明不要といいますか、シンプルに高いほどヤバいというイメージを既にお持ちでしょう。もちろん、これはその通りでして、脳出血や心筋梗塞のリスクは格段に上がってきます(泣)。
とりあえず小括としては、
「高血圧の基準は140mmHg以上。ただし、130mmHg以上で血管の病気のリスクが上昇します。」
というところです。
…となると、次に疑問に思うのは「じゃあ結局血圧は130mmHg以下がいいの?140mmHg以下でも駄目なの?」というところじゃないでしょうか?
これ、結論から言うと「それは人による。」なんですね。
とても極端な例でいうと、30歳の特に何の既往歴もない健康な人と、80歳で糖尿病、腎臓病の持病がある人で、目標とする血圧が異なるのは何となくわかるでしょう。患者さんの年齢や「リスク」を加味して、目標血圧を決めるわけですね。(糖尿病も同じで、若い人と高齢者で目標血糖が違うのは当然のことです)
ここでいう「リスク」とは
・脳心血管病(脳出血、脳梗塞、心筋梗塞)の既往がある
・高齢(65歳以上)である
・喫煙中である
・男性である
・脂質異常症、糖尿病など他の生活習慣病がある
・不整脈(心房細動)がある
・尿タンパクが陽性である
などです。(実は他にも脳心血管病の家族歴や、肥満、慢性腎臓病、血管プラークの有無などもリスクとしてカウントされる場合もあったりします)
これらのリスクの数や年齢、その時点の血圧も見て、低リスク・中等度リスク・高リスクのいずれに相当するかを評価する。…のですが、このあたり、話すとめちゃめちゃ長くなってしまうので…。すみません、割愛します!(笑)。
で、ガイドラインの提言なども含めできるだけ(私なりに誤解を恐れず)まとめると、
「全員、生活習慣の改善をまずは頑張りましょう。それでも血圧が高い場合、リスクが低めの人は140mmHgを超えたら、リスクが高い人は130mmHgを超えたら薬物治療を考慮しましょう。で、どうせ治療するなら基本は血圧130mmHg以下を目指しましょう。ただ1点だけ注意があって、75歳以上の高齢者や腎不全の患者さんは血圧が下がりすぎて逆に体に負担がかかることもあるので、とりあえずは140mmHgを第一目標にしましょう。」(1)
といったところです(本当にだいぶんざっくりですが…)。
何となくでもよいので、皆さんの治療目標のイメージにつながれば幸いです。
ちなみに、じゃあもっと低めの血圧、120mmHg以下はどうなの?
というと、実はこの降圧目標の下限を調べる研究はあまり行われておらず、少なくともここまで低めの血圧管理をすることで通常治療群と比べて予後がよくなったという研究はありません。こちらも上記と同様、過度の降圧によりむしろ有害事象が出ることもあるので、あまり積極的な推奨はできなさそうです。
最後に、「二次性高血圧」についてお話します。
これまでずっと話してきた高血圧は、正確には「本態性高血圧」といって、原因のはっきりしない高血圧のことを意味していました。ただ原因がわからないといっても大半は生活習慣、つまりは塩分のとりすぎや運動不足、喫煙、肥満などが関与している事が多いのが事実です。ひとまず何か明確な病気が背景にあってそのせいで高血圧になっているわけではないもので、日本人の85~90%はこの本態性高血圧と言われています。
一方、二次性高血圧とは何らかの原因疾患があって、その結果(二次的に)高血圧になっているものを指します。先ほどの本態性高血圧以外、つまりは日本人の10~15%ぐらいがこの二次性高血圧じゃないかと言われています。頻度の高いものとしては、原発性アルドステロン症、腎血管性・腎実質性高血圧、睡眠時無呼吸症候群、褐色細胞腫、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症などが挙げられます。(それぞれの詳細な説明は省きます)(3,4,5,6)
若い年齢で発症した高血圧、治療がなかなか効かない難治性の高血圧、低カリウム血症などのミネラルの異常を伴う高血圧、なぜか急激に悪化した高血圧、などが二次性高血圧を疑うサインになります。
当院でも高血圧の治療はたくさんの方に行っておりますが、特に原発性アルドステロン症や睡眠時無呼吸症候群に伴う高血圧はよく出会います。腎血管性高血圧、褐色細胞腫やクッシング症候群はごくたまに出会うぐらいの感じです。
これらが疑われた際には、ホルモン検査や腹部エコー・CT検査、尿検査、睡眠ポリグラフィー検査(睡眠時無呼吸症候群の検査でいびきや無呼吸指数を測定するもの)を行ったり、ガチで精査する場合には入院してのホルモン負荷試験や、造影CT、カテーテル検査などへ進むこともあります。このあたりは疑わしい疾患によります。
この二次性高血圧は、本態性高血圧の治療で用いる降圧薬の内服以外にも、手術をしたり、ホルモン治療をしたり、(無呼吸が重症であれば)CPAP療法を行ったりと、別の治療選択肢が出てきます。ですので、これらの疾患の可能性がありそうかどうか、高血圧の治療をする前の段階でしっかりと調べておくことが大事になります。
ということで、今回はここまで。
次回は高血圧の治療薬についてお話します。
- 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編:高血圧治療ガイドライン2019.
- Fujiyoshi A, et al. Hypertens Res 35: 947-953. 2012.
- 日内分泌会誌. 2010: 86 Suppl: 1-49
- Preston RA, et al. J Hypertens. 1997; 15: 1365-1377.
- Yanase T, et al. Endocr J. 2018; 65: 383-393.
- Lenders JW, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99: 1915-1942.