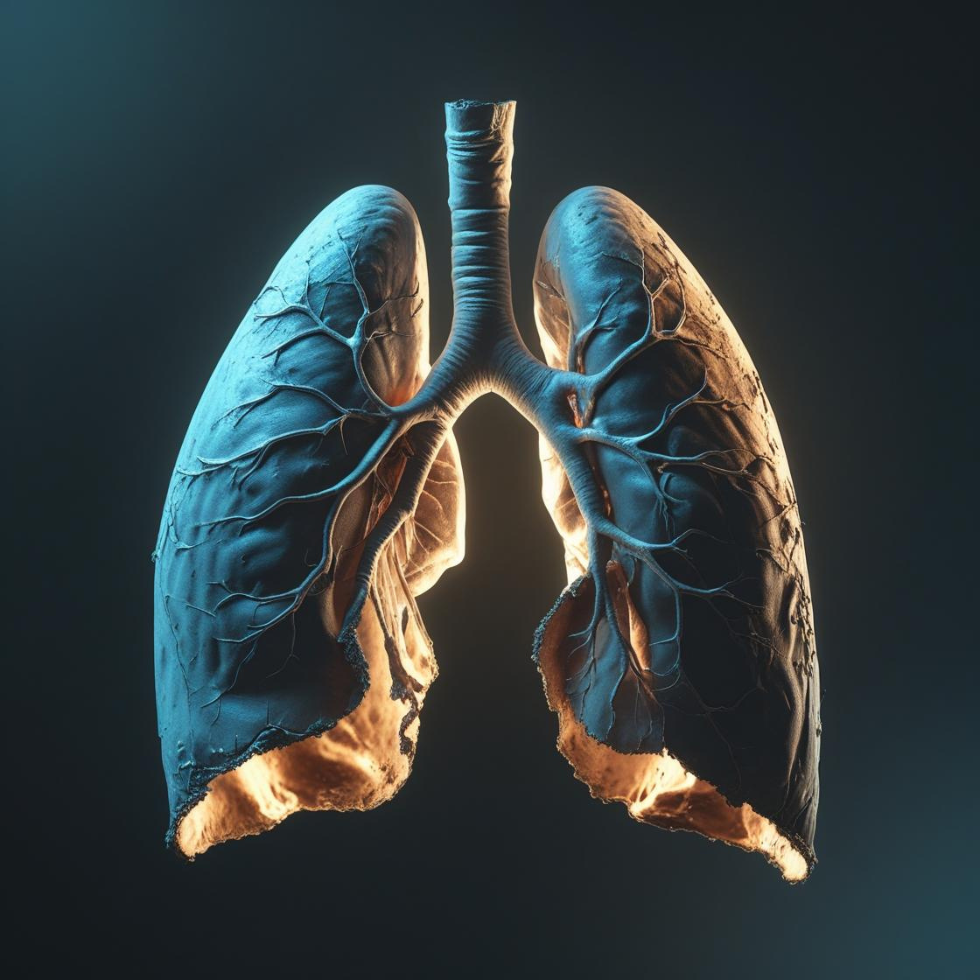さて、前回は「間質性肺炎とは?」ということで普通の肺炎との違いや、間質性肺炎を発症する原因についてお話しました。
続いては、間質性肺炎の症状についてです。
皆さん、「肺炎」というと、熱が出て、咳が続き、汚い痰も出てきて、息苦しくなってきて…というイメージがあるかもしれません。しかし、実はここでも「間質性肺炎」と「普通の肺炎(細菌性肺炎)」との違いが出てきます。
というのは、上述した症状は主に普通の肺炎(=細菌性肺炎=感染症による肺炎)でよく見られる症状なんですね。典型的には熱や咳、痰を伴い、(基本的には自然治癒しないため)抗生剤治療をしない場合1週間から遅くとも2週間ぐらいは症状が悪くなり続け、本人も「治りが悪い。これはさすがにおかしい。」と自覚し、病院を受診して肺炎と診断される、という流れが多いと思います。いわゆる急性肺炎という経過です。
一方、間質性肺炎は、前回お話したその原因にもよるものの、一般的には長期的に、具体的には数ヶ月から年単位でゆっくりと肺の障害(肺の間質の炎症)が進行していきます。慢性進行性の肺炎、いわゆる慢性肺炎という経過です。
ですので、初期は無症状であることも多いです。熱も(基本的には)出ません。間質性肺炎が進行していくと、軽い息切れや、痰を伴わない咳(空咳といいます)を感じるようになります。肺が硬く、膨らみにくくなるからですね。息切れを自覚するシーンとしては、坂道や階段の上り下り、スポーツ、入浴時などが多いです。他にも、体力低下や倦怠感、食欲不振や体重減少などが契機で見つかることもあります。
この、肺炎の進行スピードが全然違うというのが、普通の肺炎と間質性肺炎の大きな違いです。
繰り返しになりますが、間質性肺炎はゆっくりと月~年単位で進行します。ですので、なんとなく上記の症状があっても、「年のせいかな」「最近運動不足だから疲れやすいのかな」「まあしばらく様子をみるか」と軽く考えてしまいがちです。そのため病院受診が遅れてしまうことも多く、症状がひどくなってから病院を受診すると、既に間質性肺炎がかなり進行してて、(担当医も患者も)あらびっくり…(汗)ということも少なくありません。
間質性肺炎はさらに進行すると呼吸不全の状態となり、平地を歩いたり着替えなどの動作でも息切れが出て、日常生活もままならなくなることもあります。さすがにそのレベルになると患者さんも病院を受診するでしょうが、その場合は相当肺炎が進行していると予想されます。
そして、間質性肺炎は原因がわかれば(=薬剤性や膠原病などによる間質性肺炎であれば)、原因薬剤の中止や原疾患の治療、(後ほどお話する)ステロイド治療などで元の肺の状態に戻ることも期待できます。しかし進行しすぎていると、そこから治療を頑張っても完全に元の状態には戻りません。
更には、(前回お話したように)そもそも原因がわかるのは間質性肺炎全体の半分以下です。原因がわからない場合は(これも後ほどお話しますが)治療がかなり限られます。間質性肺炎の今後の進行を遅くさせる薬が使えるかどうか…といったところで、進行しきった肺炎をきれいな肺にV字回復させる薬は(少なくとも現在は)ありません。
つまり何が言いたいかというと、早期受診、早期発見がとっても重要なんです。その上で、治療の適応があるのであれば早めに開始する。これに尽きると思います。ですので定期的な健診を受けたり、おかしいなという胸の症状があれば早めに病院を受診することをオススメします。
あと、これまで間質性肺炎は「慢性進行性」と繰り返し言ってきましたが、時折「急性増悪(ぞうあく)」といって何かのきっかけで急激に悪化することがあります。感染症や手術、サプリや漢方など様々な曝露が原因となりますが、実際は原因がわからないことも多いです。
急性増悪が起きるとあっという間に呼吸不全の状態になり、死亡率もぐんと上がってしまい、人工呼吸器などの呼吸サポートを要することも多いです。(1) また、何とか回復しても後遺症が残ったり、日常生活で酸素が必要になったりと、呼吸機能がガタッと悪くなりその後の生活が大変になることもあります。急性増悪はなかなか予防できないのが現実ではありますが、ご自身の肺に間質性肺炎があることを理解し、普段からそのような曝露に気をつけるのが大切です。
(私が医師(研修医)になり、初めて自分の担当患者さんが亡くなったのも、間質性肺炎の急性増悪でした。今でも鮮明に覚えています。。。)
さて、では次に間質性肺炎の検査についてお話します。
検査は大きく身体検査、呼吸機能検査、血液検査、画像検査、病理検査にわかれます。
① 身体検査
肺の間質の炎症により肺が硬くなると、聴診にて肺が膨らむときにパリパリ、パチパチという音が聞こえます。これは捻髪音と呼ばれ、髪の毛をつまんでねじる音と似ていることに由来しています(自分の髪の毛でやってみてください)。一番大事な身体検査です。その他にも「ばち指」といって、指先が盛り上がって爪が丸くなることがあります。
② 呼吸機能検査
肺機能の検査です。肺が硬くなると肺が膨らみにくくなり、主に肺活量が低下します。肺活量は健康な人の80%あれば正常範囲とされていますが、その後の進行性の低下がないか、定期的にチェックすることも大事です。
③ 血液検査
KL-6、SP-Dという間質性肺炎の炎症のマーカーが上昇することがあります。他にも、膠原病や過敏性肺炎など間質性肺炎の背景に隠れているかもしれない自己免疫疾患に関連する抗体検査も行います。
④ 画像検査
胸部レントゲン検査で、肺の網状影やすりガラス陰影が出現したり、肺が小さくなる変化が現れます。胸部CT検査では肺を断面でみることでより正確な評価が可能です。またCT検査は間質性肺炎の診断だけではなく、病状の進行具合や治療効果の判定、また合併しやすいとされる肺癌の精査という点でもとても優れています。(2)(当院でもCT検査は実施できます)
⑤ 病理検査
肺の組織を実際に見て診断する検査です。肺の組織をとる必要があるため、気管支鏡検査で肺組織を生検したり、外科的に(=手術で)肺の一部を切除して調べたりします。
上記はすべて大事な検査になります。ただ、①~④は比較的すぐに行うことができるものの、⑤の病理検査については得られる情報が多い反面、患者さんの侵襲(負担)も大きい大掛かりな検査になります。今後の正確な治療方針の決定や予後の評価には欠かせない検査ではあるものの、いきなり全員に実施することはなく、その時点の患者さんの状態を踏まえた上で実施が望ましい場合に行うことが多いです。
(ちなみに当院では気管支鏡検査はできないので実施する場合は他病院へ紹介しております。院長も実は数少ない気管支鏡専門医なんですがね…)
…ということで、今回はここまで。
主に間質性肺炎の「症状と検査」についてお話しました。
次回は間質性肺炎の治療についてお話します。
- Kondoh Y, et al. Eur Respir Rev. 2017;26.
- Fujimoto K, et al. Eur Radiol. 2012;22:83-92.