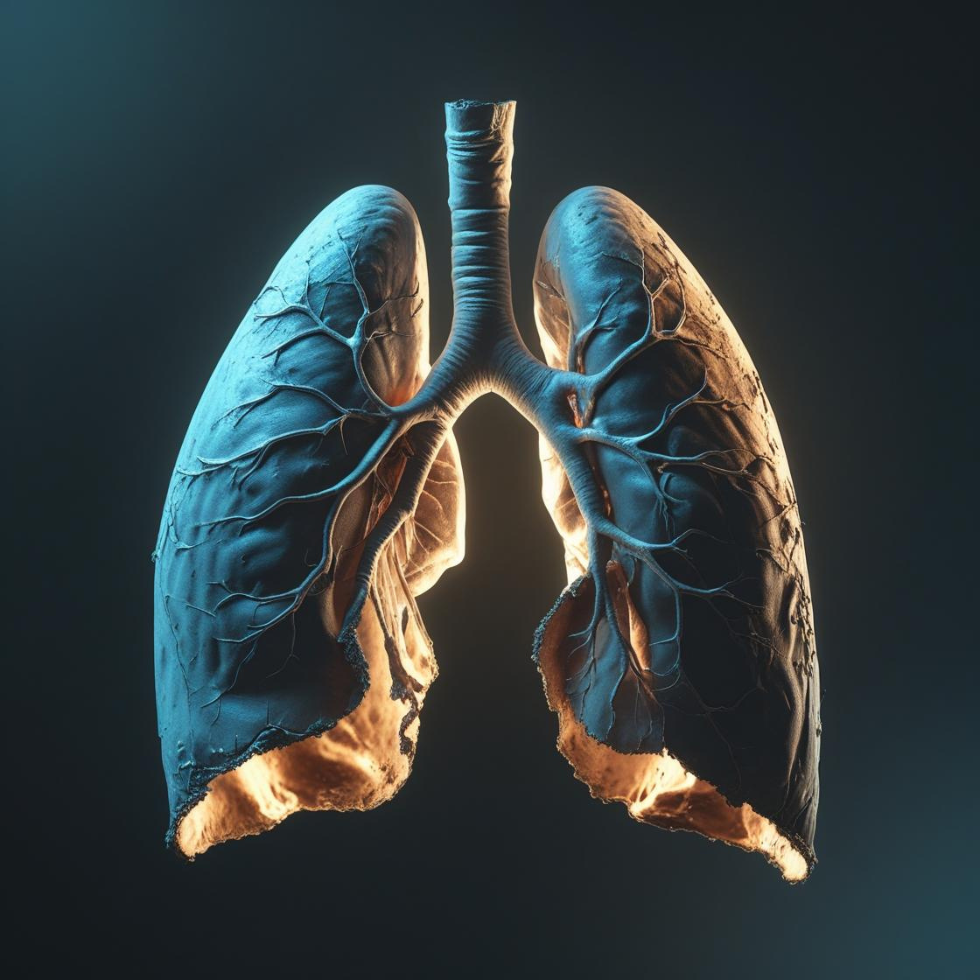糖尿病の注射製剤、2つ目はGLP-1受容体作動薬です。
インスリンと異なり、あまり名前を聞いたことがない方も多いかもしれません。
「GLP-1」というのは食事を摂取するとそれに反応して小腸から分泌される消化管ホルモンのことで、正式名称は「グルカゴン様ペプチド-1(Glucagon-like peptide-1)」、頭文字をとってGLP-1と略されています。このGLP-1が膵臓にくっつき、その結果膵臓からインスリンが分泌され、血糖値が下がる、という仕組みです。
特に「食事に反応して分泌される」というのが肝で、つまりは「血糖依存性にインスリン分泌を促進させる」=「血糖が高い時だけ作用する」=「低血糖のリスクが低い」というのも重要なポイントです。そして他にもグルカゴン分泌抑制、胃から腸への排出遅延作用などがあることから、空腹時血糖と食後血糖値の両方を低下させ、食欲抑制作用もあるため(インスリンと異なり)体重減少にも期待ができます(いいことづくしですね!)。
GLP-1は、通常は小腸から分泌されても体内のDPP-4によって速やかに分解され、生理活性を失います。そこで、体内のDPP-4によって分解されにくく、皮下注射後に血中濃度が維持できるように開発された薬がGLP-1受容体作動薬です。商品としては、ビクトーザ、トルリシティ、オゼンピック、マンジャロ、等があります。
経口血糖降下薬のコラムでDPP-4阻害薬についてお話しましたが、この飲み薬も同じ機序に作用して血糖値を下げる薬でした。ただし! DPP-4阻害薬と比較して、血糖値を改善させる作用はもちろんのこと、エビデンスの点でも圧倒的にGLP-1受容体作動薬が勝っています。特に、心血管イベント(心血管死・心筋梗塞・脳卒中)のリスクを有意に低下させることや、腎保護作用があることが多くの臨床試験で証明されています(1,2)。
前述した体重減少に関しても、GLP-1受容体作動薬は用量依存性に体重減少効果が強まることが示されています(3)。糖尿病治療において、肥満や薬剤使用に伴う体重増加はどうしても問題になるため、この体重減少効果がはっきりしている点は大きなメリットと思われます。
あ、体重減少にまつわる余談なんですが、「オゼンピック」という痩せ薬、聞いたことありませんか?ダイエットや美容に詳しい人なら、一度はネットやニュースなどで聞いたことがあるのではないでしょうか?これは上述したGLP-1受容体作動薬「セマグルチド」の商品名のことで、れっきとした「糖尿病治療薬」です。糖尿病がない人が痩せるためだけに使用する場合は自費診療となりますが、この薬を扱っているクリニックさんもあると思います(当院では行っておりません)。「楽にやせられる!」「無理な食事制限や運動は不要!」といった感じで広告宣伝されているかもしれません。
これに関し、痩せるだけの目的でこの薬を使用することを、個人的に悪いことだとは思いません。しかし、やはり楽に痩せられる!という(楽に儲けられる!的な)「楽に~できる」というのは、だいたい何か裏があるはずなんですね。笑
「くすりはリスク」といって、副作用がない薬はありません。インスリンにも低血糖や体重増加という副作用があります。そしてGLP-1受容体作動薬に関しても、頻度は多くないものの気分不良や下痢などの消化器症状、膵炎や胆嚢炎、(まれですが)低血糖が報告されています。さらにはこれらの副作用は糖尿病患者さんに投与した際の臨床試験から解析された結果であるため、それ以外の患者さん、つまりは痩せるためだけにGLP-1製剤を使用する糖尿病がない患者さんに関しては安全性のデータが乏しいのが現実です。
これらの安全性(危険性)や有効性に関することを十分理解し納得する、つまりは万が一何かあっても自己責任として受け入れるのであれば、自費診療として実施してもよいとは思います。体重効果ははっきりしているのでね。(ただ、このあたりをしっかり説明せずさっさとオンライン診療なんかで処方しちゃうクリニックも多いようです。そりゃクリニックとしては処方すりゃ儲かるので、副作用をあんまり説明したくない気持ちもわかりますが…笑)。
個人的には、この薬を使うかどうかの前に「必要以上に食事をとらず、必要以上に運動する」ことが何よりも大事なんだと思います。「なんやそれ、当たり前やないか!」と思われるかもしれませんが、その当たり前のことが継続してできている人、結構少ないもんなんです。
さて、だいぶん話が脱線してしまいました。すみません。
話をもどしますが、GLP-1受容体作動薬は1日を通じて血糖値を改善させるだけではなく、体重減少効果もあり、低血糖リスクが低く、さらに心血管リスクも有意に低下させ、さらに腎臓の保護作用もあり、とまさに2型糖尿病の治療薬としてはできすぎた薬です。
この薬ですが、作用時間によって長時間作用型と短時間作用型の2種類があります。
①長時間作用型
・ビクトーザ:1日1回注射
・トルリシティ:1週間に1回注射
・オゼンピック:1週間に1回注射
・マンジャロ:1週間に1回注射
②短時間作用型
・バイエッタ:1日2回注射
・リスキミア:1日1回注射
こんな感じで分類されますが、基本的には1週間に1回の注射ですむweekly製剤(トルリシティやオゼンピック、マンジャロなど)がよいと思っています。週1回といえど効果は十分立証済みで、かつ利便性もよく生活に支障をきたしにくいので、継続もしやすいです。
あ、前回のコラムの一番最後に、理想的な治療が難しい人(体が不自由、認知症、高齢)の余談がありましたが、このような方々にもこの週1回注射はとてもよい適応と思います(低血糖のリスクも低いですしね!)。
という感じで、この薬はエビデンスも豊富で、糖尿病患者さんにはかなりメリットが大きい薬と考えられます。「え、そんなにいいなら、全員はじめから使ったらいいじゃん」と思うかもしれませんが、本当にそうなの(そうなる?)かもしれません。ただ真面目な話をすると、このGLP-1受容体作動薬の臨床試験では、その対象となった患者さんの多くがメトホルミンを内服していたという背景があります。
個人的には、糖尿病内服薬のコラムでお話したメトホルミンやSGLT-2阻害薬、DPP-4阻害薬などの内服薬をまずはしっかり使い、それでも血糖値が思うように改善しない場合は別の内服薬(SU薬やα-GI)を追加するかGLP-1受容体作動薬を追加する、という流れがよいと考えています。
もちろん、著明な高血糖(血糖値300mg/dl以上、HbA1c 10%以上)の場合はGLP-1製剤よりも確実に血糖値を下げることができるインスリン製剤が優先されるのは言うまでもありません。
さて、長く続いた糖尿病シリーズもこれで終わりになります。少しでも読者の方の糖尿病に関する理解が深まれば幸いです。
次は、皆さんご存知、「高血圧」についてお話したいと思います。
- N Engl J Med 2016; 375: 311-322.
- Lancet 2019; 394: 121-130.
- Lancet 2021; 397: 971-984