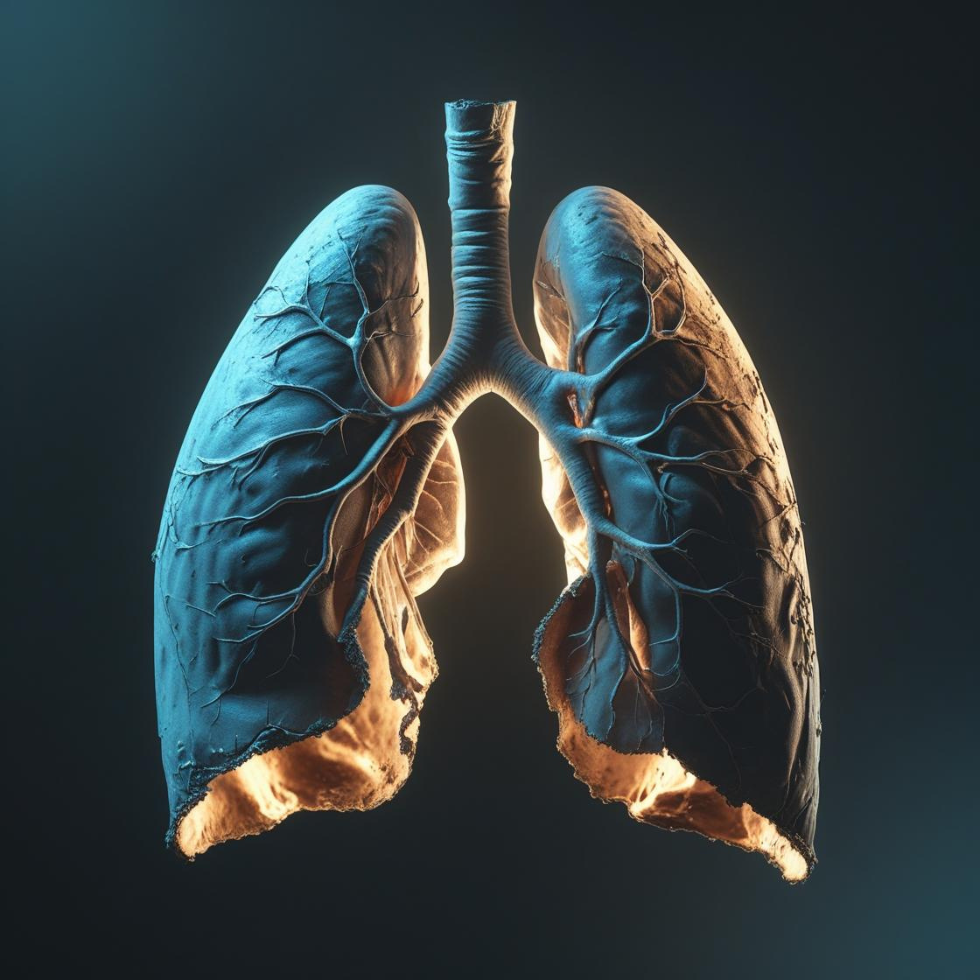ここからは糖尿病で使う注射に関するお話です。
これまで様々な内服薬について説明してきましたが、まず前提として注射製剤の血糖降下作用は内服薬よりも強力です。そして、大きく2つのジャンルにわけられます。
それは、「インスリン製剤」と「GLP-1作動薬」です。
まずはインスリンのお話から。
患者さんにインスリンの話をすると、「一度使い始めると一生ですか?」「もう末期ということでしょうか…?」と言われることがあります。費用や手技に対する漠然とした不安ももちろんあると思いますが、何よりインスリンそのものに最初から悪いイメージを持っている患者さんも多いのが現状です。
しかし…!よく考えてみて下さい。インスリンは本来体内で膵臓から生成される、血糖値を低下させることができる唯一のホルモンなんです。その分泌量が少ない、または効きが悪い時に外から補充するのがこのインスリン製剤なんです。そう聞くと、これまでご紹介した内服薬よりもむしろ天然由来(?)といいますか、そこまで悪者扱いしなくてもいいかなと…なんとなく思いませんか?(違う?)
「糖尿病① 糖尿病とはどんな病気か」で糖尿病の種類に関して少しだけ触れましたが、1型糖尿病や妊娠糖尿病、膵臓全摘後に関してはインスリン導入が必須になります。今回は内服薬で治療している2型糖尿病患者さんがインスリンを導入する場合でお話を進めます。
皆さん、インスリンは最後の手段!というイメージが強いと思います。確かに内服薬のみで血糖コントロールがつかない場合の導入が最多なのですが、大事なのは「後手になりすぎないよう、適応がある方に適切なタイミングで導入すること」です。というのは、血糖が高すぎるのにインスリン導入が遅れると、その間に膵臓の機能が低下するだけでなく、血管障害・合併症の進行につながるからです。悪い例としては、「網膜症や腎症が進行してきたからそろそろインスリンを使いましょう」といった後手の導入です。時すでに遅し…かもしれません。
ただ、インスリンを使うことで低血糖のリスクは上がります。また体重も増加します。ですので食事・運動療法は継続してしっかりと行い、インスリン量がなるべく減らせるよう頑張るのも大事です。
さて、生体における本来のインスリン分泌は実は2つに分類されます。
・空腹時血糖値をコントロールする基礎インスリン(1日中じわ~っと出ているインスリン)
・食後血糖値をコントロールする追加インスリン(食事に反応してぐっと出るインスリン)
の2つです。
インスリン療法の基本的な考えは、インスリンを注射することでこの「基礎インスリンと追加インスリンを理想的な分泌パターンに近づけること」にあります。
- 持効型インスリン(トレシーバ、ランタス、インスリングラルギンなど)
基礎インスリンに相当するのが「持効型インスリン」と呼ばれる、1日1回の注射でじわ~っと24時間効くインスリン製剤になります。基礎インスリンが減ると空腹時(食前)の血糖値が上昇してきますので、空腹時血糖が高い場合に導入されます。
- 超速効型インスリン(ノボラピット、ヒューマログ、フィアスプ、ルムジェブ、リスプロ、アスパルトなど)
追加インスリンに相当するのが「超速効型インスリン」と呼ばれる、食事の直前に打ってすぐに効くインスリンになります。食事に反応して出るインスリンの代わりですので、朝昼晩の1日3回打つ場合も多く、患者さんにとっては負担が大きくなります。
基本的には、この2種類を片方だけ、もしくは両方用いて上述した理想的な分泌パターンを再現するのが主な治療になります。(実はそれ以外のインスリンもたくさんあるのですが、それらについてはこのコラムの最後で少しお話しておきます。)
……ただ、とはいってもやはり、インスリン導入で「はいわかりました」とすんなり受け入れられる方はわずかです。ここで、インスリン導入にちょっとだけ前向きになれるお話があります。
皆さん、「糖毒性」という言葉を聞いた事はあるでしょうか?
糖毒性とは、「高血糖が続くことでインスリン分泌能低下やインスリン抵抗性増大が引き起こされ、さらなる高血糖となる」こと、いわゆる悪循環に陥っている状態です。インスリンを導入するぐらい血糖が悪い時は多かれ少なかれこの糖毒性の状態になっていると思われるため、インスリンでこの悪循環をしっかり断ち切るのが大事になります。
大量にインスリンが必要であった患者さんでも、治療の結果血糖コントロールが改善し糖毒性が解除されたあとはインスリン必要量も大幅に減り、インスリンが不要になることもあります。ですので決して「インスリンは使い始めると一生使うんでしょ?」というわけではありません。インスリンを離脱できるケースもたくさん存在します。
もう一つ、インスリンを初めて導入するにあたり私がよく活用しているのがBOT(basal supported oral therapy)という治療法です。BOTは、経口血糖降下薬と持効型インスリン(1日1回のじわ~っと型)を用いて血糖をコントロールする手法です。
前述の通り、ほとんどの患者さんはインスリン導入に後ろ向きなのが現実です。そして、インスリン治療が必要になったときにも、いきなり1日複数回のインスリン注射を行う、なんてことになると生活も大きく変化し、経済的な負担も大きくなるなど多くの理由から受け入れるのが難しくなります。一方、BOTは1日1回の注射を現行治療に追加するだけの方法であり、皮下注射のタイミングも自由に決められるためインスリンを比較的導入しやすく、特に空腹時血糖がなかなか下がらない症例にはとても良い適応と思われます。
さて、ざっくりとでしたがインスリンに関する話はこれで以上です。
インスリン導入は(というかどんな治療においてもですが)患者さん自身の病気への理解、治療の主体性が特に大事になります。好んでインスリンを打ちたい人なんておりません。ご自身のインスリン分泌状態を把握し、なぜインスリンが必要なのかを十分に理解していただき、その上で治療のゴール(目標)を決め、ご本人の生活や費用なども踏まえ、適したインスリン製剤を選択し、治療していくことが重要だと考えています。
次回はもう一つの注射製剤、GLP-1作動薬についてお話します。
私見)
前述の持効型と超速効型の代表的なインスリン製剤以外にも、中間型インスリンや速効型インスリン、およびこれらが配合されているミックス製剤、配合溶解インスリンなど他にもたくさんの製剤が存在します。しかし、「中間型」は持効型と比べて持続時間が短い、血中濃度の変動が大きい、低血糖のリスクが高いといった理由であまり使用されません。同様に「速効型」も超速効型と比べると食直前ではなく食前30分の注射が必要になり、タイミングが合わせにくいといった理由であまり使用していません。ミックス製剤は一見便利そうなイメージがあるものの実際は中途半端なコントロールになりやすく、現在の多様な治療薬を考えると優先順位は下がると言わざるを得ません。唯一、持効型と超速効型の配合溶解インスリンである「ライゾデグ」は1日1回の注射でよいためたまに使用することもあるぐらいです。
これらの配合薬は理想的な治療が難しい(諦める)状況、例えば患者さん自身での頻回の自己注射が(認知症や手足の麻痺などといった理由で)難しく、仕事終わりのご家族さんや訪問看護師が1日1回や2回打ってあげるのが限界、などといった(仕方ない)場合などで特に選択肢となると考えています。